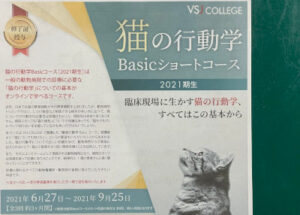【重要】お願い
診察の行き違いを防ぐために、当院にご連絡いただく前にここに書かれている内容を読まれて、ご理解いただけたという前提で、お話を進めさせていただいております。説明時間の短縮にご協力ください。
また、おたがい一生懸命頑張ったのに、無駄になったということを避けたいと思っております。
行動診療のイメージ
↓記事を書いてみたので、良かったらご覧ください。(会話形式で読みやすいと思います)


行動診療について
来院例
猫ちゃん
- 特発性膀胱炎(ストレスが原因)
- 不適切な排泄(マーキングや異所での排泄など)
- 攻撃行動
- 常同障害(尾追い行動、自傷、過剰な舐めなど)
などで受診なさっています。
犬ちゃん
- 攻撃行動(人、同居動物など)
- 過剰咆哮(”いわゆる”無駄吠え)
- 不適切な排泄
- 常同障害
- 音や光に対する恐怖症(それぞれあり)
- 心療内科(胃腸障害、食欲不振、悪化する皮膚病など)
などで受診なさっています。
*当院は、獣医行動プラクティショナー(日本獣医動物行動学会)認定の獣医師が診察する動物病院です。詳細記事はこちら
解説
当院は「『しつけ』をしない」動物病院です。
福岡では行動診療(問題行動の診察)を行っている動物病院はほぼ無いので、お困りの方も多いのではないでしょうか。当院では東京農工大学動物行動科研修医として行動診療の学びを更新しております。患者様は福岡県のみならず、他県からも診療に来られています。
多くの飼い主様が、お困りの際はまずはネット検索をして、書いてある内容だけで判断せざるを得ないですよね。一生懸命吟味し、良さそうに思うトレーナーさんに依頼して、「言うとおりにすればするほど悪化させてしまった。そして困ってたどり着いた」という飼い主様がほとんどです。なので、決してあなただけではありません。みなさんお困りで当院に駆け込まれてきます。
トレーニングだけしても改善しません。そもそも疾患が原因であった症例もたくさんいらっしゃいます。だからこそ獣医師の診察が必要なのです。
もしまだ、どこに行こうか迷っている場合は、当院にて受診なさってみませんか?
過去の自分を振り返っても、どうしてもほめるしつけの勉強を始めたばかりでは、動物中心のアドバイスになりがちで飼い主様が蚊帳の外になりがちでした。私たちは飼い主様に寄り添うための勉強も更新中です。お力になりたいと思っております。出来ること出来ないこと、それにより治療のゴールをどこにもっていくか。一緒に相談しましょう。
獣医行動プラクティショナーに加えて、先にも書いた通り定期的に東京農工大学まで行き行動診療科の研修医として学びを深め、日々情報更新に努めております。(そのため多々臨時休診が発生することを、おわび申し上げます)
また、特に問題行動が無くても「より良い動物とのつき合いを学びたい」、「正しいしつけを学びたい」という飼い主さんが多数来院されています。問題行動は、予防が第一です。
国際中医師の資格も保有しているため、メンタルケアの際に漢方を併用する事も出来ます。
学術略歴
- 一般診療
- 獣医師国家資格
- 動物行動学(行動診療)
- 東京農工大学 動物行動科 研修医
- 日本獣医動物行動学会 所属
- 2000年(日本獣医動物行動学会の前身の研究会発足時)から入会
- 獣医行動プラクティショナー ⇒ プラクティショナー紹介
- 日本獣医動物行動学会 役員(学会担当)
- 漢方
- 国際中医師(世界中医薬学会連合会)
- 動物福祉
- 福岡県動物愛護推進教育講師
当院を初めて受診される方へ
- また、【初診の方へのお願い】もありますので、ご連絡の前に、必ずこちらもご覧ください。
- 行動診療の特性上、動画や静止画を送っていただくことが多いです。原則として当院では個別のLINEでのやり取りは行っておりませんが、これらを送っていただくために行動診療の予約が決まりましたらLINE登録お願いいたします。(事前に把握できない場合は、LINEから削除しておりますのでご注意ください)⇒ LINE登録はこちら【予約後】
問題行動の診察を希望される方へ
- 当院の【問診票】の記入をお願いいたします。
- 日本獣医動物行動学会の「診察前調査票」統一様式フォーマットも、ご記入の上、ご持参下さい。
- 犬の飼い主さん用 ⇒http://vbm.jp/DogQ.pdf
- 猫の飼い主さん用 ⇒http://vbm.jp/CatQ.pdf
- 家の間取り図(この子のいる場所と状況)および写真
- メールアドレス(受け取れるもの)
- 行動の動画がある場合は、公式LINEに送ってください。(重すぎてメールに添付が出来ないため)
- ただしLineでは、連絡や相談は受け付けておりません。お電話で対応しております。通知は消しています。
特に2の日本獣医動物学会の「診察前調査票」は、時間を割いてゆっくりご記入お願いいたします。
情報が少ないと診療中におたずねするため、時間がかかり料金も上がります。
3以降の注意事項もご覧下さい。
記入の際の注意事項
- 今後の連絡のためのメールアドレスを、日本獣医動物行動学会の「診察前調査票」統一様式フォーマットに、ご記入下さい。(フォームには記入欄がございませんが、大き目の字で、空きスペースにお願いいたします)
- 診察前調査票を記入の際は、なるべくていねいにゆっくり思い出して、ご記入をお願いいたします。用紙が足りない場合は、別紙を加えていただいてかまいません。
- 今後の診察においても、行動記録をもっと丁寧に書いて提出していただくので、ここで出来るだけていねいに書くようにできると診察がスムーズに進められます。
- チェックをしにくいので、手書きでお願いいたします。
- 間取り図や生活環境や周辺の写真なども添えていただけると、より効果的です。
- 当院に初めてかかられる方は、こちらの問診票の記入もお願いいたします。
- 身体検査、臨床学的検査を行っている場合は、血液検査など検査データーも添付の上、かならずご持参下さい。(紛失した場合は、再発行してもらって下さい。難しい場合は、再度こちらで検査することもございます)
- 問題となる行動の動画などを出来るだけ撮影していただけると助かります。LINE登録をお願いいたします。
- トレーニングを行っている場合は、トレーニング動画を見せてください。
診察の流れ
- まず、診察受付時間内にお電話を下さい。(土日はご遠慮下さい)
- 上記の「診察前調査票」に、ご記入下さい。
- 調査票をご持参、もしくは郵送して下さい。
- その際に、メールアドレス(出来るだけメールの方が助かります)
- 電話番号などを、必ずご記入下さい。
- 調査票を提出後数日から数日から1週間くらい、解析にお時間をいただきます。
- 追加質問がある場合は、後日ご連絡させていただきます。
- 内容を確認の上、診療の予約日を検討するため、予約日を決める相談電話を入れる日をおたずねください。
- 診療予約を入れるためのお電話を、お願いいたします。
- 平日のお昼休みの時間に行っているため、午前の診療が混雑した場合、時間がずれる場合がございます。午前の診療終了後にスタートさせていただきますので、午前の診療がとても混雑している場合は、待ち時間がかなり長くなることもございます。また、午後からの診察に差し支えますので、診察は予約開始の5分以上前にはご来院ください(遅れると別途料金が発生します)予めご理解いただけている方のみ受付しております。
- 待ち時間に関するクレームの対応ができないため、お忙しかったりストレスを感じられる方は、当院での受診は避けられた方がよいと思います。
- 初診時は2時間(~3時間)程度、診察に時間がかかることがございます。そのため完全予約制です。
- 再診の場合は、おおむね30分~1時間(~2時間)程度かかるケースが多いです。
- 時間のずれも含めて、十分余裕をもってお越しください。
- 行動診療の診察料(通常の診療費と別料金設定です)がかかります。病気の診察が入った場合は、別途診察料がかかります(薬やその他の治療にかかったものは別)
- 初回の診療で、今後の相談をさせていただきます。
- 診察後は、再診の他に初めのうちは1(~2)週に1回程度の再診になることが多いです。
- 間をあけて時間をかければうまくいくというものでは無く、実践して問題点や達成したことなどの早めの微調整をしていくのが早期解決のコツです。期間があくとかえって悪化するケースもあります。
- その際にメールで記録の報告を送っていただきます。メールアドレスを必ずご記入下さい。(メールがない場合は、FAXでのやりとりになります)それらのツールがない場合は、事前にご相談ください。
- 間をあけて時間をかければうまくいくというものでは無く、実践して問題点や達成したことなどの早めの微調整をしていくのが早期解決のコツです。期間があくとかえって悪化するケースもあります。
- 当院のみでは対応が難しいと判断した場合は、日本獣医動物行動学会の個別症例相談(有料:認定医によるアドバイス:対応獣医師の名前はお伝え出来ません)を利用させていただきます。その際は、会に払うシステム料及び当院の対応料が別途発生します。
- 一番初めにお伝えした通り、行動診療は通常の診療以上に、飼い主様の取り組みの度合いで治療成績が変わってくる診療科目です。そのため飼い主様のご協力は不可欠であることを、再度お伝えさせていただきます。
- 2回目以降は、診察後に次回の再診予定を相談させていただきますので、スケジュールが分かる物をご持参下さい。(キャンセルの可能性がある場合は、予定を入れないようにお願いいたします)
問題行動は、病的な要因で起こされていることもあります。その為、医学的検査が必要になる場合がございますので、行動診療だけではなく一般診察も行っております。また、薬の投与などが必要な場合は、随時血液検査も行います。当院で精査出来ない症例の医学的検査につきましては、当院が紹介させていただきます病院と連携(セカンドオピニオン)させていただく場合がございます。
飼い主様の気付きと、精査、評価が、とても大切な診療科目です。
ご希望に添えず獣医師の精神的負担による体調不良に陥るような状況になった場合は、治療の継続が困難になってしまいます。
一緒に手を取って歩んでいけるように、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
料金
- 基本料金:1時間まで:6,000円(税別)
- 以降、30分ごとに3,000円(税別)
初回の診察
初回は2時間以上かかります。(最低12,000円~)
午前の診療終了後なので、時間が食い込むことが多々ありますので、お時間に余裕を持ってお越しください。(遅い時間からのスタートにしたいのですが、カウンセリングが終わらない事があるため、前もってご理解とご協力お願いいたします)
追記:初診時に私たちからお伝えしたいことはたくさんありますが、初回は飼い主様の緊張もありお話をしても伝わっていないケースだったり、飼い主様が私たちに伝えたい情報量が莫大で時間が経過してしまい、私たちから飼い主様に伝えたいことを伝えきれなかったりする事例がたまにあります。その為、あまり長くならないようにし、足りない部分は次回の診察に回すように変更しました。
今後もいろんな事例を経験し、飼い主さまにも私たちのとっても、お互いによりよい診療を行っていくために少しずつ調整していきますので、ご了承お願いいたします。
2回目以降(不安定な状態の時)
- 1~2時間かかります。(最低6,000円~)
- はじめのうちや状態が安定しない時は、1(~2)週で再診を受けていただきます。
安定後
- 30分~1時間かかります。(最低6,000円~)
- 特に大きな変化が見られなくなり、2週間に1回程度のフォローアップで良いレベルになった場合には、再診のサイクルを伸ばしております。その診断をした上、ご相談させていただきます。
報告書提出
決められた期限までに、報告書の提出をお願いいたします。
- 診察終了時に、飼い主様から次回の提出期限のご確認をしていただきますようご協力お願いいたします。
経過観察の報告書の事前提出がない、もしくは期限に間に合わない、もしくは診察の来院時にまとめて提出される場合は、そのチェックは診察が開始してから行います。そのため、診察時間が長くなるため料金に加算されます。
料金設定の理由
- 行動診療は、料金設定を見ると高いなと思われるかもしれません。しかし診察に時間をとても要します。
- 一般的な検査はもちろん別途発生しますが、機械を使わない検査として、目の前の動物を観察し判断していく技術が必要となります。
- また、1日で診療できる数も限られてしまいます。有料セミナーや学会などにも積極的に参加したり、1~2か月ごとに東京まで研修に行ったり、スキルアップのための教育費用(経費)もかなりかけています。
これらの事をご理解いただけると助かります。
その他
問題行動の治療には、遺伝要因、育った環境、発育時の栄養状態、基礎疾患、過去の経験(知り得ないことも含め)、現在の環境要因、家族(他動物も含め)構成、本能による行動など、ありとあらゆる諸々の要因が複雑に絡まっている場合があります。
その為、飼い主様自身の努力だけでは解決出来ない場合もございますし、すべての問題行動を解決出来るわけではありません。
当院は動物行動学を学び、常に最新の情報を取り入れる努力をし、適切なアドバイスが出来るように学びを続けている動物病院です。
↓こちらの記事もご覧ください